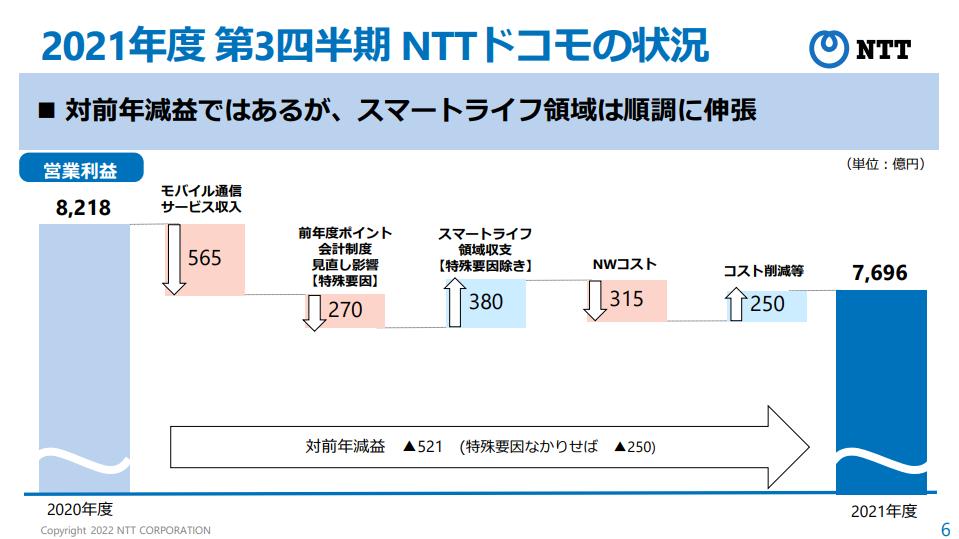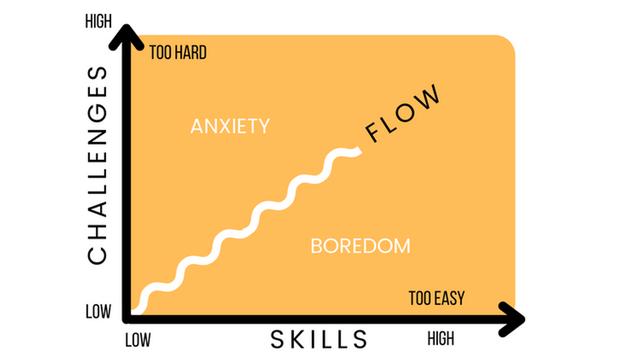【シュンペーター賞受賞記念】量子コンピューター研究者を「年収500万」で雇う日本は「野生化」できるか 早稲田大学商学学術院教授・清水洋氏インタビュー
――「シュンペーター賞」受賞、おめでとうございます。
ありがとうございます。「比較制度分析」の青木昌彦先生、「進化経済学」のリチャード・ネルソン、「インダストリー・ダイナミクス」のスティーブン・クレッパーなど錚々たる受賞者の系譜に、自分が加わるというのは少し場違いな気もしますが、とても光栄です。
――受賞の対象となった研究について、教えてください。
清水洋氏私は、社会に大きな影響を与えるGeneral Purpose Technology、すなわち汎用性の高い技術のイノベーションについて研究しています。古くは「蒸気機関」や「電気」、戦後なら「レーザー」、現在ならば「人工知能」などが、それに該当します。
これらのイノベーションに成功すると、さまざまなところで使われるため、社会の生産性が大きく向上します。また、このようなイノベーションは企業の競争力に直結します。かつては蒸気機関や電気を発明した英米が世界経済を牽引し、レーザーでは、日米独がしのぎを削りました。現在は人工知能の基幹技術をめぐって米中が激しく競争しています。
――汎用性の高い技術のイノベーションに成功する条件とは何なのでしょうか?
かいつまんで言うと、ヒト・モノ・カネの流動性を高めること――私はそれを「野生化」と呼んでいます――が、イノベーションを起こしやすくする条件と考えられています。つまり、アメリカ社会のように、人々が転職を繰り返し、企業や生産設備などのスクラップアンドビルドが盛んで、またベンチャーキャピタルによる資金提供が活発になれば、それだけイノベーションが起こりやすくなるわけです。
一方、私の研究では、アメリカのような流動性の高い社会は、たしかにイノベーションは起こりやすくなるものの、達成される技術水準が低くなってしまう傾向があることを、半導体レーザーの技術革新の調査から実証的に明らかにしました。つまり、スタートアップを促進すれば、イノベーションが次々と生み出され、万事OKとなるわけではないという議論です。これは従来の常識とは異なる視点であり、それが今回の受賞につながったのだと思います。
――なぜ流動性の高い社会だと、達成される技術水準が低くなってしまうのでしょうか。
アメリカでは、ある企業で新技術が開発されると、それに関わった担当者がその新技術を別のサブマーケットに持ち込んでひと儲けしようとする傾向があります。つまり、研究者やエンジニアがその企業からスピンアウトして、新たなスタートアップ企業を立ち上げたりするわけですね。
魅力的なサブマーケットを獲得するには、他の人より早く参入することが大事ですから、技術者の間でスピンアウト競争が起こりやすくなります。そうすると、スピンアウトするタイミングが、下記の図の(1)の矢印が示すようにtからt-1へと前倒しされていきます。その結果、(2)の矢印が示すように、既存の技術進化の軌道は、図の破線のように、早い段階で収束してしまうのです。
スピンアウトのタイミングと技術進化(清水洋『野生化するイノベーション』195頁より)要するに、流動性の高い社会では、手っ取り早く成果を出すために「手近な果実(low-hanging fruit)」ばかりをターゲットにしてしまい、幹の太い技術が育たなくなってしまう可能性があるのです。
――なるほど。では、日本のようにヒト・モノ・カネの流動性が低く、スピンアウトが起こりにくい社会の方が、技術水準が高くなるわけですね。
基本的にはそのような傾向になりますが、ただ注意しなくてはならないのは、すでに技術が成熟しているt+1の段階に達しているのに、いつまでも同じマーケットで競争を続けていると、次第に価格競争に陥り、利益を出せなくなってしまうことです。これは今、多くの日本企業が陥っている状態だと思います。
ですから、アメリカ型社会も日本型社会も一長一短で、必ずしもどちらが良いとは言い切れないというのが私の考えです。大事なのは、このようなイノベーションに関する構造的なメカニズムをしっかり理解して、それぞれの社会に則した改善点を考えていくことです。
――でも、やはりアメリカ型社会の方が優れているんじゃないですか? 今回のコロナ禍でも、日本は自前でワクチンを開発できず、アメリカ製のワクチンに頼らざるを得ない状況なのですから……。
たしかに、日本の製薬会社は未だに新型コロナウイルスワクチンを開発できない一方で、アメリカのファイザー社とモデルナ社はいち早くコロナワクチンの開発に成功し、世界中に輸出しています。いま両社は空前の売上をたたき出していますね。
――今回の受賞対象の研究を発展させた形で一般向けに書かれたというご著書(『野生化するイノベーション:日本経済「失われた20年」を超える』)の中で、イノベーションには「アニマル・スピリッツ」が重要であることが示唆されていました。日本もアメリカのように社会を「野生化」させて、アニマル・スピリッツを取り戻すことが必要なのではないでしょうか?
『野生化するイノベーション:日本経済「失われた20年」を超える』
今回のコロナワクチンについて言えば、「精神論」に帰するのは間違っているでしょう。アメリカが他国に先駆けてワクチンを開発できたのは、ドナルド・トランプ前大統領が180億ドル(約2兆円)もの巨額の予算を投じ、官民一体となって開発を進めたからです。そもそも日本とアメリカでは、研究開発に使える予算が文字通り「ケタ違い」だったのです。
――日本の「ワクチン敗戦」は、反ワクチン運動の盛り上がりを嫌った製薬会社が、ワクチン開発に消極的になったことが原因の一つだとも言われていますが。
私の専門領域ではないので、その点について詳しいことはわかりません。しかし、経営学者の視点から見れば、そもそもケタが違う予算の差を、「積極的/消極的」などの精神論で埋めようとすること自体に無理があります。そのような発想は、太平洋戦争で、彼我の圧倒的な物量の差を無視して、開戦に踏み切ってしまった日本軍部の過ちを想起させます。
そもそも、日本では「アメリカは、民間企業が活発な自由競争を繰り広げていくことによって、経済成長を遂げている国である」という思い込みがあるような気がします。しかし、それは幻想です。もちろん、そのような側面もあるにはありますが、イノベーション研究の視点から見ると、じつはアメリカでは民間企業のイノベーションを国防総省などを中心とした国がしっかりと下支えしているのです。国家の存在感は圧倒的です。
たとえば、アメリカではもともとワクチン開発は「安全保障」の一環として捉えられています。なので、トランプ政権が2兆円の予算をつける以前から、国防総省の傘下の国防高等研究計画局(DARPA)からワクチンの基礎研究に巨額の予算が投入されてきました。日本企業が自力だけで競争するのは難しい状況でしょう。
2015年においてアメリカの国が支出する研究費のおよそ半分(48%)が国防総省関連のものです 。インターネットやGPS、あるいは集積回路やレーザーなど、現在の大きなビジネスの基盤となっている技術は、すべて国防予算から生み出されてきたと言っても過言ではありません。アメリカは国防予算によって基礎研究をおこない、そこから生まれたイノベーションを民間が利用して、経済成長を遂げてきたわけです。
一方、戦後の日本にはそのような国防予算はありません。しかも国全体の研究開発費のうち、国が支出する割合は20%を切っており、国際的に見ても極めて低い水準です。
――日本もアメリカのように、軍事研究をしないといけないのでしょうか。
必ずしもそうとは思いません。イノベーションのコスト負担の在り方は、その国の歴史や国民の価値観、経済システムなどによって異なってくるのは当然です。日本は日本なりのやり方を考えていけば良いと思います。
ところが、私が危惧しているのは、これまで説明したような日米の構造的な違いを理解せずに、表面的にアメリカを真似して、とにかく社会の流動性を高めればイノベーションが活性化するに違いないと短絡的に考えてしまう人たちがいることです。
もし、現在の日本でヒト・モノ・カネの流動化だけを進めてしまうと、きっと困ったことが起こるでしょう。つまり、企業はせっせと「手近な果実」だけをもぎはじめる一方、かわりに基礎研究を行う組織も予算もないという事態になるはずです。
そうなれば、田中耕一氏(島津製作所でソフトレーザー脱着法を開発)や中村修二氏(日亜化学工業で青色発光ダイオードを開発)のように、民間企業の研究者がノーベル賞を取るような例も見られなくなってしまうかも知れません。
アメリカの民間企業が「手近な果実」だけをもいでいても大きな問題になっていないのは、あくまで圧倒的な国防を中心とした政府の予算に支えられているからなのです。そこを理解せずに、日本社会の流動化だけを進めればイノベーションのタネが全くない国になってしまいかねません。
――それは目も当てられない悲惨な状況ですね。では、日本はやはり社会の流動化を進めない方がいいのでしょうか?
それは難しい問題です。私は、日本が今の社会のままでグローバル競争を勝ち抜いていくのは厳しいと考えています。
先日、研究者コミュニティの中で衝撃を呼んだニュースがありました。トヨタの中央研究所(豊田中央研究所)が量子コンピューターの研究者を募集したのですが、なんとその給与条件が年収500万円から1000万円だったのです。イノベーション競争が激しい量子コンピューターの世界で、その条件で世界に伍していく優秀な人材が得られるとは到底思えません。
――なぜトヨタほどの一流企業が、このような条件でしか人材を募集できないのでしょうか?
量子コンピューターのように、技術革新がハイペースで進んでいく世界では、あるスキルがいつ陳腐化・無効化するかわかりません。もしあるスキルが無効になった場合、アメリカではその研究者を整理解雇して、必要とされる他のスキルを持つ新たな研究者を雇います。
しかし、日本では判例上、労働者の保護が強いので、それができません。一度、研究者を雇ったら、いくらそのスキルが無効になっても容易に解雇できず、企業はずっと雇い続けるしかない。そのリスクを勘案すると、とても「年収3000万円」とかは提示できないというわけです。むしろ、スキルはそこそこでも、他の分野の仕事でもがんばってやってくれる人材を求めてしまうのも理解できます。
人材の流動化は日本の積年の課題ですが、今のところ高スキル人材の流動化が遅々として進まない一方で、低スキル人材だけが非正規雇用という形でどんどん流動化してしまい、非常に歪な形になっています。これは非常に複雑で難しい問題ですが、やはりこの部分でバランスの取れた「野生化」を進めないと、イノベーションの復活は見込めないと思います。
----------
清水洋(しみず・ひろし)
早稲田大学商学学術院教授
1973年神奈川県横浜市生まれ。一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。ノースウエスタン大学歴史学研究科修士課程修了。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでPh.D.(経済史)取得。アイントホーフェン工科大学フェロー、一橋大学大学院イノベーション研究センター教授を経て、2019年に早稲田大学商学学術院教授に就任。主な著書に『ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノベーション:半導体レーザーの技術進化の日米比較』(2016年、有斐閣、日経・経済図書文化賞受賞、高宮賞受賞)、『野生化するイノベーション:日本経済「失われた20年」を超える』(2019年、新潮選書)などがある。
----------


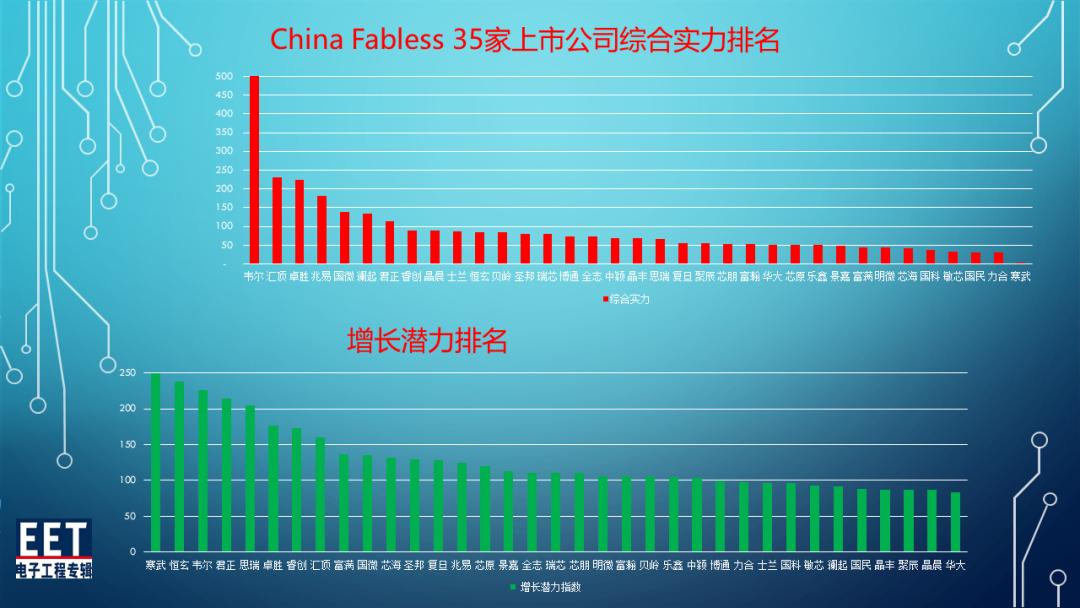
![[Excel] 写真や図などの画像を貼り付ける方法 [Excel] 写真や図などの画像を貼り付ける方法](https://website-google-hk.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/drawing/article_results_9/2022/3/9/72539ecbf7413c05e4465b39ca06e8e0_0.jpeg)