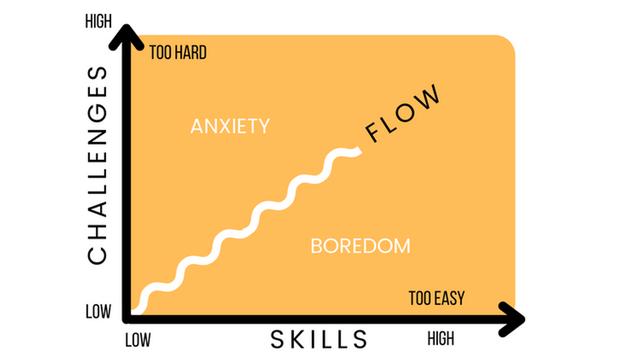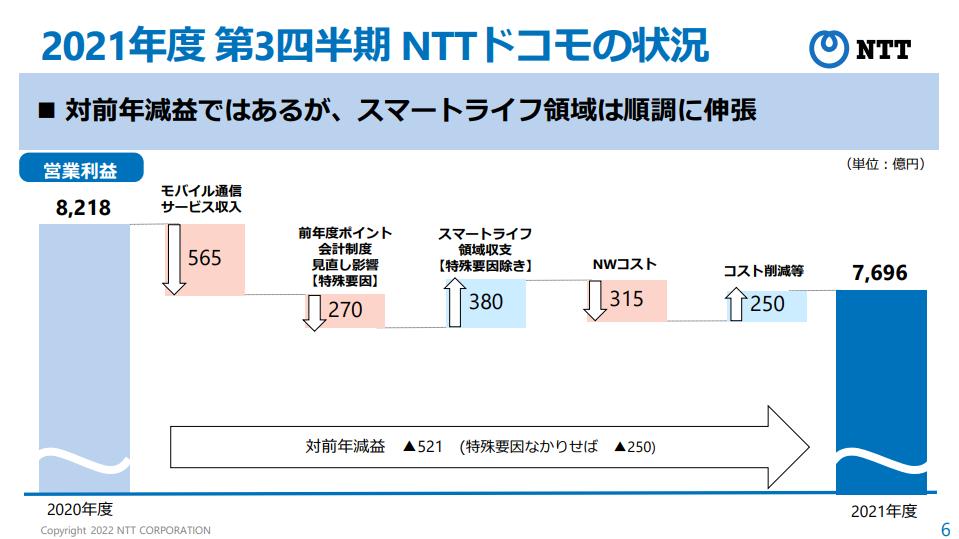ピクサーの成功を支えた知られざる天才、アルヴィ・レイ・スミスとピクセルの歴史(前篇)
2007年、『ピクサー・ストーリー』と題された新しいドキュメンタリーがミルヴァレー映画祭で上映された。それはピクサー・スタジオの創設者たちが、全く新しい種類の映画をつくりあげていったころの破天荒な日々をつづったものだ。
彼らがつくりあげようとしていたのは、鮮やかな色とテクスチャーに彩られ、信じられないほど生き生きとしたキャラクターたちが、ぶっ飛んだ知識に裏打ちされた会話を交わしながら進行していくフル・コンピューターアニメーションの映画だった。
その後に行なわれたパネルディスカッションで、インタヴュアーが挑発的な質問を繰りだした。「ちょっとばかげた質問かもしれませんが、カウンターカルチャーやサイケデリックな世界とピクサーとの間には、なにか関連性がありますか?」
ステージ上のパネリストたち──ピクサー発展の中心人物であるエド・キャットマルとジョン・ラセター──は、気まずい沈黙に陥った。何世代にもわたって子どもたちに愛され続けるディズニーの傘下で働く彼らにとって、ドラッグとカウンターカルチャーはあまり触れられたくない話題だ。しばらくしてようやく口を開いたラセターはこう言った。「ここにアルヴィ・レイ・スミスは来ているかな?」
ピクサーの歴史から消された男
もしあの髭面の豪快なピクサーの共同設立者スミスにその質問に答えるチャンスが与えられていたとしたら、いかにもLSDは自分のクリエイティヴな方向性を定める手助けをしてくれたし、それがピクサーの文化とテクノロジーの両方をかたちづくったのだ、ともろ手を挙げて認めただろう。
スミスがピクサーを離れたのはちょうど実際の映画がつくられ始めたころだが、その映画のフレームの1コマ1コマすべてがスミス抜きでは存在しえなかった。スミスが解き放った新技術があったからこそ、完全にコードとアルゴリズムのみから映画を生みだすことが可能になったのだ。スミスはピクサー以前と以降の仕事においても、最初のデジタルペイント・ソフトに多大な貢献を与え、われわれが映像を操る能力に変革をもたらした機能を編みだしていた。
だがスミスがそのときステージ上ではなく会場の後方に座っていたという事実は、別のことを物語っている。彼の貢献と名声との間の不協和音だ。スミスはコンピューターサイエンスにおいても人を楽しませることにおいても、ユニークな人物だ。点滅するオシレーター上に描かれた原始的な線画の時代と、めくるめくコンピューター画像による没入的なヴァーチャル世界との間に橋渡しをしたのは、紛れもなく彼だった。
その一方で、ラセターがほのめかしたように、60年代の世界観を自分が触れたものすべてのなかに吹きこんだのも彼だった。その多くはいまだにわたしたちの感覚のなかに残っている。それでも、健康的なエゴと生き生きとした話し上手な性分の持ち主であるスミスは、ラセターからの呼びかけのあとも──そして部屋の中に多少の笑いが起きたあとも──会場後方の席についたまま口を開くことはなかった。
それは自制だった、と見るべきだろうか。「歴史という点から見れば、彼はピクサーの歴史からも、コンピューターグラフィックスの歴史全般からも、完全に消されているという気がします」と以前ピクサーで同僚だったパム・カーウィンは言う。「いま現在あなたが使っているフォトショップの技術はすべて、基本的にアルヴィが生みだしたものです」。
自律走行車やAR技術でさえもがそうだ。なぜなら「そういった技術はすべて、画像処理や機械視覚に関するものだからです……アルヴィとその同僚たちこそが、そういった技術のすべてをこの世界にもたらしたのです」。
ピクサー映画が画期的だったのは、その映画の解き放つ感情が、人間の演技が放つ感情と同じように生き生きとしていたという点だ。PHOTOGRAPH BY CAYCE CLIFFORD
だが、現在77歳になるスミスの偉業は過去にとどまらず、世界はまだ彼の先走る才能に追いついていかなければならないようだ。この夏、スミスが満を持して出版した著作『A Biography of the Pixel(ピクセルの歴史)』[未邦訳]には、デジタル表現の大統一理論が展開されている。
本書はダグラス・ホフスタッターの『ゲーデル、エッシャー、バッハ あるいは不思議の環』の精神を受け継ぐ深くて挑戦的な一冊であり、科学とヒーローたちと暴君たちの複雑に入り組んだ物語が、時に21世紀初頭を巡りながら、長らく予見されていたデジタル・コンヴァージェンス[編註:デジタルテクノロジーの発達によってあらゆるメディアがひとつに統合され、収斂していくこと]へと向かっていく。
ヴィジュアル、テキスト、オーディオ、ヴィデオといったほとんどすべての表現がコンピューターの世界へと移ったが、その世界はじつは直観に反して、物理的なこの現実世界に全くひけをとらないほどリアルだ。しかもそれは暗喩的な意味で同等なのではない。スミスによれば、それは文字通りの意味で同等なのだ。
「すべてはただの波にすぎないんだ」
スミスはこの第二の現実を「デジタルライト(Digital Light)」と呼ぶ。それは誰もが、森の内奥にいるのでもない限り、つねに目や耳に入ってくるものだ。ただ、その言葉をつくりだしたのはスミスではない。その言葉を最初に発したのは、10年ほど前、そのタイトルのもとにスピーチをしてくれないかと頼んできたある会議のオーガナイザーだった。「それはわたしの望むものすべてを内包する言葉だった」とスミスは言う。「人がピクセルを使って行なうあらゆることの側面が、その言葉のなかに凝縮されていたんだ」。
デジタルライトは長く入りくんだ科学的プロセスを経てこの世に姿を現した、とスミスは説く。その誕生の物語はピカレスクロマンさながらの波乱万丈のストーリーであり、図らずもそこに登場することになった主役たち──ジャン=バティスト・ジョセフ・フーリエ、ウラジーミル・コテルニコフ、アラン・チューリング──の人生を、スミスは何かにとりつかれた系図学者のような情熱をもって描きだす。
光の性質、サンプリング、計算に対する彼らの業績を総括したあと、スミスはアナログとデジタルの現実の間に違いはないという確信に満ちた主張を展開する。それは彼が何十年にもわたって抱いてきた信念だ。コンピューターグラフィック専門のジャーナリスト、バーバラ・ロバートソンは、とあるカフェでの彼との会話を思い出す。しばらく黙って物思いにふけった後、スミスはおもむろにこう言ったのだ「だって、すべてはただの波にすぎないんだ」。
言っておくと、このピクセルの生い立ちを描いた本の主題は、わたしたちが普通に思い浮かべるようなものではない。ピクセルというのがスクリーン上の細かい正方形の一点だという誤った思いこみは、この際一旦捨て去ろう。スミスの説明によるとピクセルとは、何らかの意識的につくりだされたコンテンツの一要素が何らかのディスプレイ上に表示されるという、ふたつのプロセスの産物だ。
つまり、みんながスクリーン上に見ているのはピクセルではなくて、そういったピクセルの「表現」なのだ。みんなが見ているのは、「デジタルライト」だ。え、じゃあピクセルそのものはどこにあるのかって? ピクセルとは単なる概念だ。この違いに気づけば、「デジタルライト」が現実に劣るものではないということがはっきりわかるはずだ。21世紀には、それは同等のものなのだ。
「ピクセルをディスプレイの要素から切り離すというごく単純な考え方を聞いただけで、そのテクノロジーを理解していない人たちにとっては画期的に思えるでしょう」とロバートソンは言う。
このコンピューターグラフィックスの歴史は、いわばスミスの影の自伝だ。その部分は560ページの大著のちょうど半分あたりから始まる。スミスがそこで再現してみせるのは、有名なシタール奏者のラヴィ・シャンカールがルーカスフィルムのスミスのラボを訪れたときのことだ。
シャンカールは、アルゴリズムによって生まれた花が開く様子に魅せられ、称賛に満ちた声で「アルゥゥゥヴィィィィ!」と叫ぶ。その瞬間から、スミスはピクセルの物語に忘れがたい重要人物として姿を現し、さらに自らをかたちづくり、ほとんど殺しかけた人々を登場させる。つまりスティーブ・ジョブズ、ジョージ・ルーカス、そしてアレックス・シュアという無名の自称アニメーションのパイオニアといった面々だ。この革命に参加したひとりとして、スミスはわたしたちを21世紀の変わり目へといざなう。当時世界はデジタルコンヴァージェンスのとば口に立とうとしていた。
「何かもっと芸術味があることを」
アルヴィ・レイ・スミスが本書を生み出すまでに10年かかった。いや、ひょっとしたら50年かもしれない。それはこの本の始まりを、スミスが執筆を始めたときと考えるのか、あるいは本書に書かれた人生を生き始めたときと考えるのかによる。
「一度、頭の中だけですけど、アルヴィの人生を脚本にしてみたことがあるんです。実際、すばらしい映画になるんじゃないか、と思いました」とスミスの妻、アリソン・ゴプニックは言う。アリソンがスミスに出会ったのは、人生もかなり終盤に入ってからだ。「最初のシーンは、ニューメキシコの砂漠から始まります。そこに金髪の小さな男の子がひとり。まわりには馬たちがいてサボテンが立ち並んでいる。そこへホワイトサンズから発射されたロケットが地平線の彼方にあらわれ、男の子はそのロケットを見上げます」。
実際、スミスはまだ2歳にもならないころ、ニューメキシコのラスクルーセスに住んでいた。1945年のトリニティ核実験の爆発音が、100マイル(約160km)離れたその町でも聞こえたとスミスは語っている。彼の父親は当時戦地にあって不在だった。両親は結婚して子どもをつくりはしたが、お互い二度と会えないかもしれないと思っていた。父親は結局戦争から帰還し、テキサス州最北部の近くにあるクローヴィスという小さな町で家畜飼料の事業を営むことになった。
スミスは成績優秀で、特に数学に優れた才能を見せた。だがプロの芸術家である叔父と時間を過ごすのも大好きだった。ジョージ叔父さんが自分のアトリエに入ることを許していたのはスミスただひとりで、少年時代のスミスはそこで叔父さんがカンヴァスを張り、油絵具とテレピン油を混ぜあわせ、顔料を使って真っ白なカンヴァスに生命を生み出す様子を黙って眺めていた。
また、近くにあるホワイトサンズ・ミサイル実験場の科学者たちのもとを訪れたとき、コンピュータープログラミングを少しだけ体験する機会があった。ニューメキシコ州立大学では電気工学を学び、さらにスタンフォードへ進んで人工知能の研究を始める。だが彼がカリフォルニアで学んだのは、コンピューターに関することだけではなかった。
「移って次の年には、わたしの髪はかなり長くなり、ゴールデンゲート・パークでありとあらゆるドラッグやら何やらをキメてブラブラしていた」とスミスは言う。そしてLSDをやったあと、彼はこう確信したのだという。「自分はただのプログラマーには向いてない──何かもっと芸術味があることをやる必要がある」と。
芸術とコンピューターとの結婚
それが実現するまでには、もう少し時間がかかった。スミスは結局、セル・オートマトンの研究に向かう。セル・オートマトンとは、規則に基づいたシステムにより生成され自己複製を続けるデジタル有機体のことだ。博士号をとったあと、スミスはニューヨークへ移って大学で教職に就いた。そこで『サイエンティフィック・アメリカン』誌の71年2月号の表紙を飾ったセル・オートマトン・パターンのデザインも行なっている。だがニューヨークという街の快楽には馴染んだものの、大学での研究生活はスミスにとって満足のいくものではなかった。
70年代の半ば、ニューヨーク工科大学で仕事をしている間、スミスはつねにインスタントのシリアルスナックを食べていた。「たしか、いつもグレープナッツ・シリアルだった」とスミスは言う。「仕事をどんどん進めて何ひとつ見逃さないようにするために、食事はつねに大急ぎだった」 PHOTOGRAPH BY DAVID DEFRANCESCO
72年12月、スミスがニューハンプシャーのスキー場の斜面を滑降していたとき、ニット帽がずれ落ちて顔にかぶさった(のちに、その帽子の内側にあるタグには「視覚障害者が編みました」と書かれていたことに気づいたという)。そのせいで、コントロールを失った他のスキーヤーが自分の方にまっすぐ向かってくるのが見えず衝突。スミスは右大腿骨に重度の螺旋骨折を負い、それから3カ月間、胸から爪先までを完全にギプスで固定されて過ごすことになった。
「1日15時間、ノンストップで考え続け、世界全体を一から考え直した」とスミスは言う。彼がずっとやりたかったのは、コンピューターと芸術との融合だ。だがいつのまにか、彼の中から芸術が失われていた。「わたしは自分にこう言ったんだ。『アルヴィ、おまえはとんでもない間違いをやらかしたぞ』とね」とスミスは言う。
スミスはニューヨーク大学の職を辞してカリフォルニアに戻った。1年間バークレーの友人宅の床で寝て、何かが起こるのを待った。そして実際、何かが起こる。74年5月のある日、友人のリチャード・シャウプがスミスに声をかけ、自分の職場であるゼロックス・パロアルト・リサーチ・センター(PARC)へ来ないかと誘ったのだ。そこではコンピューター科学者たちのチームが、コピー機業界に君臨する企業の資金を使ってコンピューターに革新をもたらす発明に取り組んでいた。
「スーパーペイント」と呼ばれるシャウプ自身のプロジェクトはその計画にあまりなじむものではなく、周囲から受け入れられているとは言えなかった。それは世界初のインタラクティヴなカラーグラフィック・プログラムで、基本的にはカラーテレビのディスプレイにペイントブラシ・ソフトで絵を描くようなものだったが、ユーザーが画像をつくりだし、操ることを初めて可能にしたプログラムだった。
スミスはこれを見て、クスリの錠剤を思わず手から落とすほどの衝撃を受けた。「デジタルライト」の発見だった。「わたしは13時間ぶっ続けでそのプログラムをプレイし続けても、まだその場を離れたくなかった」と彼は言う。「これこそ芸術とコンピューターとの結婚だった!」
すばらしき混沌の世界
当時、コンピューターにフルカラーのグラフィックなどめったにお目にかかれなかった。たったひとつの画像をつくりだすのにさえ、フレームバッファとして知られる膨大な量のメモリーが必要だった。「ディスプレイにひとつの絵をアップするには、その絵を何かに一旦格納しておかねばなりませんでした。その『何か』が50万ドルもするんです」とPARCでパーソナル・コンピューター・チームを率いていたアラン・ケイは言う。リサーチ・センターのラボには遅くて思い通りに動かないフレームバッファしかなかったが、それが「スーパーペイント」の誕生を可能にしたのだった。
スミスはこの「スーパーペイント」とフレームバッファがあれば、アニメーションをつくりだすことができると直感した。「わたしたちは描いたものを動かすことができると、すぐに気づいた」とスミスは言う。彼はラボを訪れては、映画的なシークエンスをつくるようになった。アニメの人物が目をパチパチさせたり、目玉をぐるぐる回したりするような画像だ。
スミスはPARCに入りたくてたまらなかったが、ラボは彼をフルタイムで雇おうとはしなかった。最終的にはケイの助言を受けて、PARCの幹部たちはスミスを確保しておくローリスクな方法を編みだした。まるでひとつの装置を借りるときのように、購入注文をスミスに発注することによって報酬を支払うことにしたのだ。PARCは「専門的な労働サーヴィス」に対し、857時間分の注文を発注することになった。
まもなく、デヴィッド・ディフランチェスコというヴィデオアーティストがラボに出入りするようになった。スミスはシャウプのシステムに見栄えのいいインターフェイスを構築し、いまでは何百万もの人たちが当たり前のように使っているパーソナル・グラフィックス・プログラムの最初のアイデアをかたちにしつつあった。スミスはそのソフトウェアを使ってアニメーションをつくり、ディフランチェスコがその映像を記録した。すばらしき混沌の世界だった。
髪をポニーテールにしたスミスは、74年にゼロックス・パロアルト・リサーチセンターで働き始めた。そこでスミスは瞬時に「スーパーペイント」というデジタル映像プログラムにとりつかれることになる。 PHOTOGRAPH BY DAVID DEFRANCESCO
だが、彼らののどかな楽園は長くは続かなかった。ある日、幹部の一団がスミスとディフランコに、今後はモノクロ部門を強化すると告げ、「スーパーペイント」はお払い箱になったのだ。アルヴィ・レイ・スミスに対する購入注文はキャンセルされた。
コンピューターグラフィックスだけでできた劇場用映画を
それでも、スミスは自分の使命をすでに見出していた。コンピューターグラフィックスの未来を築きあげることだ。スミスとディフランコはスミスの白いフォード・トリノに乗りこむと、州間高速道路をぶっ飛ばして、あまりその分野のメッカとは言いがたいユタ大学を目指した。なんとかそこで新たな仕事を見つけようと考えたのだ。
ユタ大学のコンピューターグラフィックス研究者たちは、どちらかというとコンピューター支援による設計のような実用的なアプリケーションに特化した研究を行なっていて、スクリーン上にカラーピクセルをぶちまけるようなサイケデリックな描画技術には興味がなかった。結局ユタ大学はスミスとディフランコを雇わなかったが、彼らとまったく同じ考えをもっている人物として、最近ユタ大学を卒業したばかりのエド・キャットマルの名前を彼らに教えたのだった。
まだ30歳にもなっていないキャットマルだったが、コンピューターグラフィックスはエンターテインメントに革命を起こすという世間とは逆をいく考えを本気で信じていた。キャットマルは、ニューヨーク工科大学というあまり似つかわしくない場所に職を得ていた。響きはマサチューセッツ工科大学に似ているが、75年当時のその大学の評判は、ほぼ卒業証書を量産する三流大学というものだったのだ(その評価は現在ではかなり改善されている)。
ロングアイランドの北岸に位置するその大学は、グレート・ギャツビーのような見かけの邸宅をいくつも所有していた。大学の運営を仕切っていたのはアレックス・シュアという自称「教育起業家」で、出どころのわからない潤沢な収入源を持っていた。第二のウォルト・ディズニーを目指しているのだろうという噂をつねに否定していたが、おそらくそれを否定し続けたからこそ、人はみなシュアの目標はディズニーになることだと認識していた。
シュアは『テューバのタビー』という子どものためのオーケストラ曲をもとにしたアニメーションの制作に大金を注ぎこんでいた。そのプロジェクトに携わるアニメーターを100人も雇っており、その制作の一部を自動化してくれることを期待してキャットマルを雇ったのだった。
エドウィン・キャットマルは早い時期から、コンピューター・グラフィックスがエンターテインメントの世界に革命を起こすと確信していた。 PHOTOGRAPH BY CAYCE CLIFFORD
ユタ大学の関係者から話を聞いたキャットマルはスミスとディフランチェスコに声をかけ、ふたりはすぐに飛行機に飛び乗ってロングアイランドへ向かい、彼のグループに加わる。グループの拠点は、例の邸宅のひとつのガレージの上にあった。人当たりが穏やかなモルモン教徒のキャットマルは、すでに家族もちだったが、すぐにスミスと仲良くなった。
「アルヴィは黒くて長い髭を生やし、髪を長く伸ばしていましたが、そんなことは気になりませんでした。彼は頭がよくて、人を惹きつける魅力のある人でした」とキャットマルは言う。キャットマルにとって何よりも嬉しかったのは、いつか一本丸々コンピューターグラフィックスだけでできた劇場用映画をつくるという自分の夢を、スミスが共有してくれたことだ。ふたりはその夢のことを「あの映画」と呼んでいた。
アルファチャンネル発明でアカデミー賞
スミスはキャットマルの事実上のパートナーになった。当時のコンピューターグラフィックスはコンピューター科学のへりにしがみつく継子に過ぎず、まだまだ原始的だった機械の限られた力に制限されていた。だが彼らは、やがてムーアの法則として知られることになる事実がその状態を変えることを確信しており、自分たちの研究分野を強化して、コンピューターとエンターテインメントをつなぐ要の存在になろうと考えた。
シュアも全面的に協力し、18フレームバッファを数十万ドルも出して購入してくれた。装備を整えたチームは、短いアニメーション映画をつくりはじめた。彼らの敵は「ジャギー」だった。ジャギーとは粗い描画処理のふちに現れるギザギザした端のことだ。このジャギーをなくすには、アンチエイリアス処理という技術が必要になる。この処理を行なってより高解像度のグラフィックを生み出すためには、高い計算能力を持ったコンピューターと、高い技術力が必要だった。
追加されたバッファのおかげで、スミスとキャットマルは色のコンセプトを大きく進化させることになる。それがアルファチャンネルだ。通常は赤、緑、青の基本三原色のカラーチャンネルをさまざまに組みあわせてフルカラーのパレットをつくりだすのだが、ふたりはそこにピクセルの透明度をコントロールする要素をプラスしたのだ。
オブジェクトの透明度を時間とともに微調整することにより、その動きをぼやかして、初期のデジタルアニメーションの試みを台無しにしていた不快なカクカクとした動きを修正することができるようになった。
みんないったんアルファチャンネルを使い始めると、誰もがその存在をごく自然に受け入れるようになった。「誰かにアルファチャンネルを発明したのはアルヴィだと言っても、それがどういう意味なのか、みんな理解できないでしょう。いまやアルファチャンネルは、グラフィックに関わるすべてのものの基本に最初から組みこまれているからです」とグレン・エンティスは言う。
エンティスは当時ニューヨーク工科大学で講義を受けていた学生で、のちに『シュレック』や『マダガスカル』に関わったグラフィックス会社を共同設立した人物だ。スミスと同僚たちは後日、アルファチャンネル発明の功績によりアカデミー賞を受賞することになった。これはスミスがもっているふたつの技術部門のオスカーのうちのひとつだ(もうひとつはスーパーペイントの発明に与えられたもので、シャウプとの共同受賞だった)。
※後篇はこちら


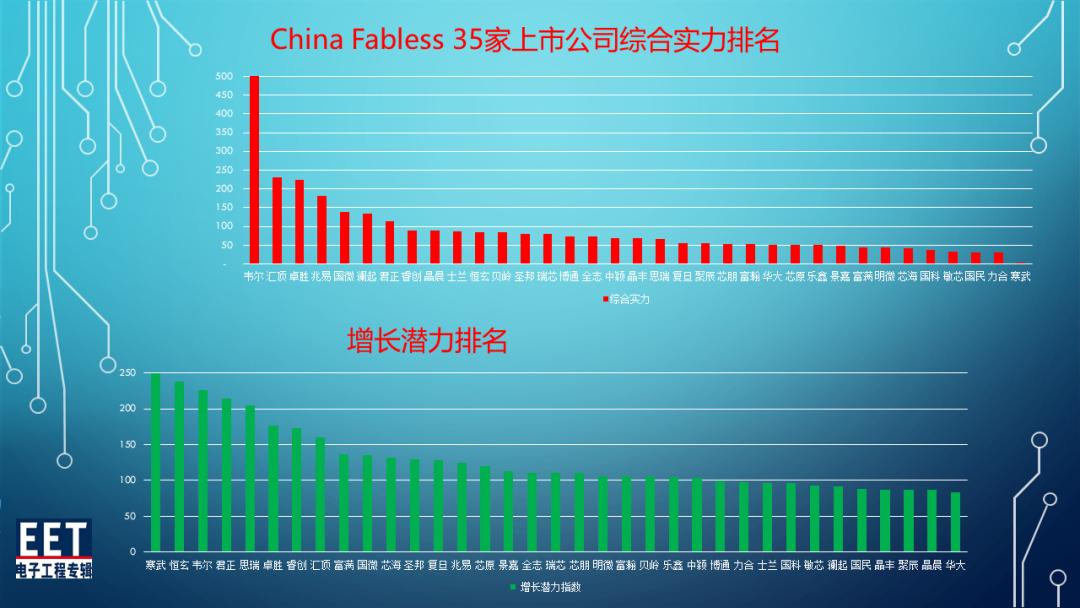
![[Excel] 写真や図などの画像を貼り付ける方法 [Excel] 写真や図などの画像を貼り付ける方法](https://website-google-hk.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/drawing/article_results_9/2022/3/9/72539ecbf7413c05e4465b39ca06e8e0_0.jpeg)